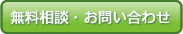
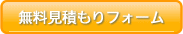
|
 | 会社設立の流れ -会社設立前の準備について- |  |
ここでは、個人事業を法人化又は独立開業する際に必要な
【会社設立前の準備について】【会社設立の手続きについて】【会社設立後に必要なこと】
の流れで、簡単に説明いたします。 |
| ① 会社名(商号)を決める |  | 新会社法施行後は、類似商号の規制が緩和されたので、同じ所在地に、同じ商号がある場合や大手企業のように世間一般に広く知れわたった商号でなければ、問題ありません。
また会社名は、漢字以外のローマ字・カタカナ・ひらがなでも登記可能です。 |
| ② 登記(本店)所在地を決める |  | 登記申請をした所在地で管轄税務署が決まります。しかし、所在地によって支払う税金が変わってきますので事前に調べておくと良いと思います。
<参考>法人の税金について
法人の税金は、法人税・法人住民税・法人事業税の3種類になります。
法人税の税率は、資本金1億円以下の中小法人の場合、課税所得が800万円までの部分については22%、800万円を越えた部分については30%になります。
法人住民税は、事務所のある地域によって税率が変わります。個人の住民税と同じように、所得割と均等割という2つの種類があります。その税率は、地方公共団体によって若干異なりますが、通常は法人税の17.3%となります。(資本金1億円以上又は法人税額が年1,000万円以上になると20.7%)
法人事業税は、税率は所得金額によって変わってきます。所得金額400万円までは5%、400万円~800万円までは7.3%、800万円以上になると9.6%です。(資本金1億円以上又は年間所得金額2,500万円以上になると、5.25%、7.665%、10.08%になります。) |
| ③ 事業目的を決める |  | | 内容には具体性を持たせることが必要です。将来、行う予定にしている事業も入れておくことも可能です。しかし、事業目的にあまり統一性がないと、銀行融資を受ける際に信用を損なう可能性がありますので、注意が必要です。 また、古物商や人材派遣業など許認可が必要な事業もありますが、会社設立当初から事業目的に入れておくことも可能です。 |
| ④ 資本金の準備 |  | 新会社法施行(平成18年5月)後は、1円でも株式登記が可能です。ですが、会社設立することが目的にならないよう注意が必要です。独立起業して、会社を維持運営していくのであれば、ある程度の資金力がなければスタートを切れません。
また、資本金の金額ですが、独立起業当初は1,000万円未満で法人登記されることをお勧めします。消費税が2期分免税されます。消費税法が改正されたため、平成16年までは、2年前の売上高が3,000万円だったのが、1,000万円を超過すると消費税の納税義務者になるよう改定されてしまいました。そのため、先程言いました法人設立日から2年間消費分税が「免税」されるということは、売上金額から本来であれば、税務署に支払わなければならない税金を利益として計上できることになるということです。 |
| ⑤ 発起人(出資者)・役員(取締役会設置)を決める |  | 発起人は、1株以上の出資が必要です。新会社法施行以後は、「募集会社設立」と「発起人会社設立」が可能になりました。最近、独立起業される方のほとんどが、発起人=役員=取締役になり、他人に出資者を募ることもせず、また本来必要な、取締役会も設置せず一人株式会社の形態で登記します。
この場合、今後想定外の会社買収などを防ぐために、「株式の譲渡制限」を付けておおく必要があります。また、役員(取締役)の任期も従来は最長2年だったのが、最長10年まで延長できるようになったため、ほとんどが「任期10年」にされています。 |
| ⑥ 事業年度を決める |  | | 法人の決算月を決めます。通常は、会社設立月の前月を決算月にします。理由は、先程の消費税の免税措置を最大限に生かすためです。 |
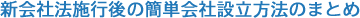 |
1. 株式譲渡制限する。
2. 取締役会や監査役を設置しない。
3. 取締役を社長(発起人)1人にし、任期を10年にする。 |
|
これが、個人事業主に毛が生えたようなもっともシンプルな株式会社設立の形態と言えます。
|